図面を見て、なんとなく形のイメージは掴めてきた…でも、「じゃあ展開図を描いてみて」と言われると手が止まってしまいませんか?
「どこから描き始めればいいの?」 「つながりがわからなくなる…」
そんな時は、いきなりペンを持たずに30秒だけ「情報の整理」をしましょう。 この準備をするだけで、パズルのピースがパチパチとはまるように、展開図がスムーズに描けるようになります。
ステップ0:描く前に整理すべき「3つの情報」

描き始めたはいいけど、途中で線が重なったり、形が崩れちゃうんです…。
いきなり本番の紙に描き始めるのは、地図を持たずに森に入るようなもの。 まずは裏紙の隅っこに、以下の3つをラフにメモ書きします。目的は「迷いをなくす」ことです。
- 面の一覧(パーツ出し): 「正面・右・左・上・下・奥」など、必要な面が全部でいくつあるか数えます。
- 面どうしのつながり(リンク): 「正面の右隣は『右側面』」「正面の上は『上面』」と、隣り合う関係を確認します。
- 曲がり方(アクション): そのつながりは90度曲がるのか? それとも別の角度か? 「谷折り・山折り」をメモします。
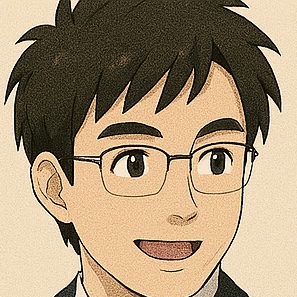
『正面—上面=谷90°』みたいに、自分だけの暗号でいい。この下準備が、実は一番大事な工程なんだ。
ステップ1:実際に描いてみよう(基準→接続)
整理ができたら、いよいよ清書(本番)です。 ここでも「迷わないための鉄則」があります。
「基準面」を決めて真ん中に描く
まずは、展開図の中心となる「親」を決めます。 基本的には「一番面積が大きい面(正面図や底面)」を基準にすると、安定して描き進められます。
上下左右に「子」をつなげていく
基準面(親)の上下左右に、隣り合う面(子)を描き足していきます。
- 寸法の写し間違いに注意: 正面図の高さが100mmなら、接続する側面図の高さも必ず100mmです。
- 線の意味を描き込む: ただの線ではなく、「ここは折り曲げ線」と分かるように、破線や一点鎖線で区別するか、端に「曲げ」とメモしておきましょう。

なるほど、真ん中を決めてから、花びらが開くように描けばいいんですね!
ステップ2:描いた展開図を「切る」
描けた!と思って終わりにしてはいけません。 特に初心者のうちは、描いた図面をハサミで切るまでがセットです。
紙は嘘をつきません。切ってみることで、脳内のイメージと現実のズレ(認識のズレ)を教えてくれます。
- ルール①: 外周の実線だけをカットする。
- ルール②: 折り線(点線)は切らない。
- コツ: 定規を当ててカッターで切ると、仕上がりがプロっぽくなり、組み立て精度も上がります。
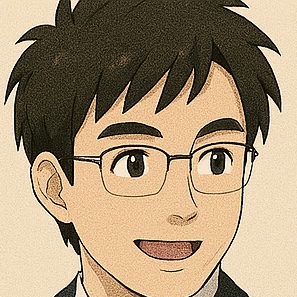
『あれ?ここがつながらないぞ?』『面が一個足りない!』。そう気づけたら合格サインだ。紙がミスを教えてくれたんだからね。
ステップ3:実際に「曲げて」立体にする
最後は組み立てです。ここでの「指先の感覚」が、将来的に複雑な図面を読む力に変わります。
- 折り筋をつける: 曲げ線に定規を当て、カッターの背中などで軽くスジを入れると、ピシッと綺麗に曲がります。
- 角度を意識する: なんとなく曲げるのではなく、「これは90度」「これは45度」と意識して角度を決めます。
- 完成チェック: 元の図面(三面図)と見比べて、形は合っていますか?

紙が立ち上がって立体になった瞬間、すごくスッキリします! プラモデルみたいで楽しいかも。
まとめ 「描く・切る・曲げる」で展開図はマスターできる
展開図が苦手な人は、頭の中だけで完結させようとしています。 プロほど、迷った時は紙を切ったり、簡易的なモデルを作ったりして確認するものです。
- 整理: 描く前に「面のつながり」をメモする。
- 描く: 「基準面」から広げるように描く。
- 体験: 実際に切って曲げて、答え合わせをする。
失敗しても紙なら数円の損です。 何枚も描いて、何回も失敗して修正するうちに、ふっと「切らなくても頭の中で組み立てられる瞬間」がやってきます。 それが、あなたが「図面をマスターした」証です。
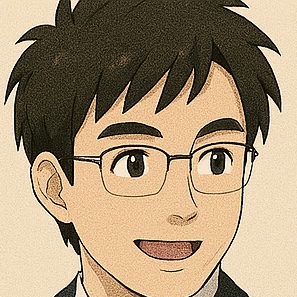
展開図をサラッと描ける人は、現場でも一目置かれる。この『紙工作』こそが、最強のスキルアップ法なんだよ。
関連記事(次の一歩)
基礎ができたら、少し難しい「斜め」の展開にも挑戦してみましょう。




コメント